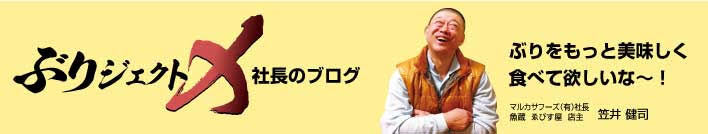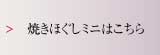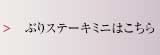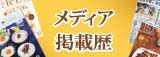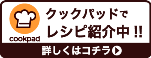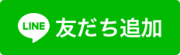ブリジェクトX ~社長のブログ~
きのこの加熱方法で、旨味アップ!
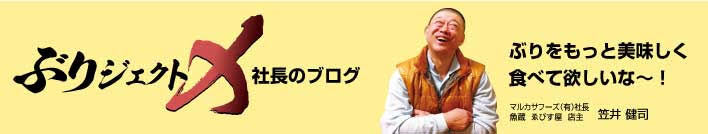
こんにちは!氷見天然ぶり専門店「魚蔵 ゑびす屋」の笠井です。
おうち鰤茶漬けの開発秘話、ご購読ありがとうございます。
最後は皆さんのご家庭でも馴染みのある
「きのこ」
きのこは、今回いろいろ学ばせてもらいました。
干ししいたけに代表されるように、きのこ本体の中には、旨み成分が、タップリ入っている!と、思い込んでいたので、試作中は、思うような味が出ないので、なぜ?と、考え込むことが、多かったように思います。
結論から言うと、きのこの旨みを引き出すポイントは、乾燥、と、加熱温度です。
キノコは80%〜90%が水分です。乾燥すると水分が蒸発し、アミノ酸や糖分、香りが凝縮されます。また、スポンジ状の空気の隙間が潰れて、歯ごたえがよくなります。
つまり、きのこの中の水分を蒸発させることで、味が濃縮し旨みがアップします。
また、きのこの旨味成分は「グアニル酸」と言いますが、実は、生のきのこには、この「グアニル酸」は入っていないのです。
中にあるのは、RNA(リボ核酸)という物質で、このRNAが、きのこの中に含まれる「酵素」で分解されることで「グアニル酸」が出来るのです。
そして、この酵素は、60℃ぐらいで、最も活性化するといわれ、それ以上の温度だと失活してしまいます。
つまり、きのこを旨みをアップするには、
(1)きのこの中の水分をへらす
(2)きのこを、60℃ぐらいで、
じっくり加熱して、多くの「グアニル酸」を生み出す。
この2つの、調理をする必要があるわけです。
今回、こうしたきのこの調理科学から、当社は、60℃で加熱乾燥することで、じっくり「グアニル酸」を作り出し、同時に、きのこの水分を蒸発させ旨みを濃縮。
その後、高温で短時間加熱して、きのこの旨みをアップしました。
今回、使ったきのこは、3種類
しいたけ
えのき茸
エリンギ
この考え方に基づき、調理しました。
今後は、その他のきのこでも、商品化したいと考えてます。


手軽さと旨味がアップしたおうち鰤茶漬けは、11/17頃リニューアル新発売予定です。販売開始致しましたら、いち早く皆様にご案内させて頂きます。
どうぞお楽しみに。
魚蔵ゑびす屋 笠井健司
- 2022.11.15
- 16:17
おうち鰤茶漬け旨み、味もリニューアル!
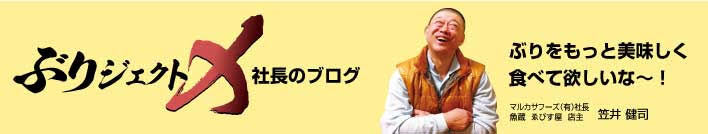
こんにちは!氷見天然ぶり専門店「魚蔵 ゑびす屋」の笠井です。
おうち鰤茶漬けのリニューアルに合わせて
実は・・・味の面でも、
2つほど、改良いたしました。
① あっさり味だが、旨みが多い
食事される時間帯が、朝や夜のことが多いことを考慮して、あっさり味は、そのままに旨みをふやしました。普通の醤油より、旨み成分であるアミノ酸含有量の多い(約1.5倍から2倍ほど)魚醤を使い、酒の量を増やし、旨みを増しました。
あっさり味にこだわったのは、胃腸にやさしい食事をお客様にしていただきたかったからです。
朝は、まだ本調子ではないので、胃腸の負担を少なくしたい。夜は、勉強や、仕事をするための夜食なので、食事をすることで、血糖値を上げて、パフォーマンスを下げないようにしてもらいたい。
こうした気持ちがありました。
② 血合肉を食べやすく
血合肉に、包丁の切り口を付け、海洋深層水で血抜きを行い、その後、黒米塩麹に漬け込むことで、臭みを取り、美味しくお召し上がれるよう工夫しました。
血合肉には、鉄分などが豊富で、できれば、お客様の健康のためにも、食べていただきたい部位です。
食べる場面や、お好みで唐辛子、胡椒、醤油など調味料をかけていただいて、自分だけのオリジナルのお茶漬けをお試しください。
私は、今、午後の小腹用に、ヒハツ(ロングペッパー、沖縄県では、しま胡椒)を、小さじ1ぱい、かけて食べています。
ピリッとした辛味で、口がヒリヒリするのですが、香りが爽やかで、体が、じんわり暖かくなってきます。また、内臓から体があたたまるので、体調改善にもおすすめです。ぜひ皆さまも、お試し下さい。
次回は、旨みきのこぶり茶漬けの紹介をしたいと思います。
笠井健司

- 2022.11.15
- 11:47
リニューアル!おうち鰤茶漬け 3分で、本格生茶漬け!
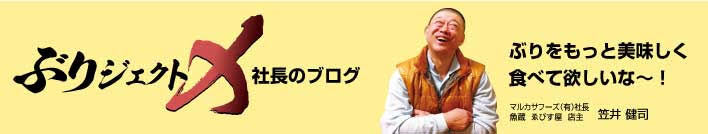


当社の「ぶり茶漬け」は、そんな受験生を応援したい
という趣旨から、開発が始まりました。
当時、私の子供が、受験生ということもあり、親御さん方の心情が他人事ではなかったのです。
その上、ぶりは、「出世魚」の横綱!。運気上昇や、大事な人への応援には、ぴったりの食材だと感じました。
また、魚は、消化も早い!疲れた脳を活性化させる夜食用に、ぶり茶漬けは、最適ではないかと考えました。
その後、黒米塩麹で熟成したぶりを、コロコロカットにした、
ギフト用の鰤茶漬け、ぶりステ-キの切り身を使ったおうち鰤茶漬けなどを販売しました。
その方は、会社経営者で、残業が多い時期の自分と社員の夜食用として購入されていました。
ちょっとした残業時に、食べたい。休憩時間の関係もあり、調理時間を短くしたいとのことでした。
そこで、今まで必要だった解凍の手間を無くし、より簡単に温め調理できないか、考えました。
今までは、事前に解凍していただく必要があり、流水解凍で15分、冷蔵庫で数時間かかりましたが、長い時間レンジで加熱してもよい、レンジ対応袋にする事で、解凍せず、凍ったまま加熱できるようになりました!
加熱蒸気用の切れ込みを入れる手間もナシ!
冷凍庫から取り出して、電子レンジで3分でお召上がりいただけるようになりました。

ご飯とお湯さえあれば、3分で、召し上がれます。
ぜひとも、受験生、や、繁忙期の社員さまの夜食用に
お求めください。
リニューアルした鰤茶漬けは今月中に販売開始予定です!

- 2022.11.08
- 17:13
レシピ ほぐしぶりの手巻き(氷見ぶり焼きほぐし 西京味噌)
発酵食品のキムチには、腸内環境を調えてくれる効果も期待できます。ぶり焼きほぐしの西京味噌を具材に使うことで、ダブルの発酵づかいにもなりますね。
●材料(2人分)
サンチュ…1袋
キムチ…100g
ごはん…適量
韓国海苔…適量
④自由に巻いていただきます。
・お子さまには、サンチュ、韓国海苔、おにぎり、ぶり焼きほぐしの組み合わせで!
・大葉、えごまの葉で巻いてもおいしくいただけます。
発酵食品のキムチを食べることで、腸内環境を調え、暑い夏を乗りきりましょう。

レシピ ほぐしぶりの焼きそば(氷見ぶり焼きほぐし 照り焼き、西京味噌、塩風味)
卵と焼きほぐしぶりのタンパク質に、たっぷりのネギので栄養バランスも抜群のメニ ュー。
ぶりに含まれるビタミンB1は、ネギと一緒に食べることで、身体への吸収が増します。疲労回復効果を高めることも期待できます。
●材料(2人分)
ネギ…適量
蕎麦つゆ…適量
油…大さじ4
②フライパンに油を加えさっと混ぜ、麺を焼き色がつくまでそのまま焼きつけます。(表面がカリッとするくらいまで炒める)
③①と焼きほぐしぶりを盛りつけます。
④そばつゆにつけながらいただきます。
・きざみのりをたっぷりかけてもおいしくいただけます。

おいしいレシピ ほぐしぶりのパスタ(氷見ぶり焼きほぐし レモンペッパー)
●材料(1人分 、子ども分だと2人分)
子供用には、マグカップに入れてもいいですね。

この仕事を始めたわけ
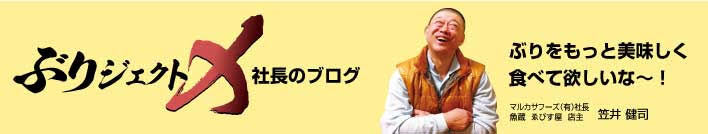
投資トレーダーからの転職
海に魚がいない!
魚の加工を始める
自分で作って自分で売る!
他には無い“ゑびす屋”名物誕生
投資トレーダーからの転職
私、笠井健司は、1960年富山県氷見(ひみ)市で海鮮問屋の長男として生まれました。
すくすくと田舎の港町で育った私は、地方の若者の多くがそうであったように、大都会、東京に憧れるようになっていました。
猛勉強の末、皆が憧れる東京の大学に合格することができ、卒業後は、銀行に就職。外国為替などの売買を行う花形部署でトレーダーをやっていました。
ある日、とんでもないミスを犯してしまいました。
「このままでは千万単位の損失だ…」
トレーダー画面に向かいながら真っ青になり、慌てて売買を閉じたのですが、時すでに遅し。数千万の損失を出していました。
「東京でうまくいかなかったら、氷見に帰って家業を継ぐ」
そう親と約束していたことが胸の奥にずっとあり、これがきっかけで、銀行を辞めて氷見に帰って来ました。
海に魚がいない!
氷見に戻ってからは、家業である海鮮問屋を継いでいました。
漁師が獲った魚を、市場で買い付け、店に卸すのが仕事の海鮮問屋。
バタバタとしながら5〜6年過ぎ、仕事にも馴染んで来た頃、とんでもないことが起こりました。
海に魚がいない!
富山湾の魚が激減したのです。氷見市場の水揚げも大幅に減りました。
私は、人生で初めて「売るものがない!」という経験をしたのです。
海には魚がいて、漁師さんが獲り、それを毎日買い付ける、そんな当たり前のことが根本から崩れたのです。
魚の加工を始める
「こんな不安定な生活ではいけない」
そう思った私は、魚の加工を始めることにしました。
加工魚なら、大漁の時に仕入れて月々売って行くという安定した商売ができるはずです。
アジやサバの干物から始めました。
おつきあいのあったスーパーや量販店の方達にも好評で、たくさん買っていただきました。しかし当時はデフレの真っ最中。
大量に作っても利益がほとんど出ない日々が続いていました。
自分で作って自分で売る!
そんなある日、うっかり冷凍室に閉じ込められてしまいました。
従業員も帰ってしまった後で誰もいません。
死を覚悟しました…。
大学時代の空手が功を奏し、この時は、凍った扉を押し開けて何とか脱出できました。
しかし、私は、深く考え込んでしまったのです。
このまま量販店に卸していても薄利多売になるだけだ。
自分が死んでも、お金もない、何も残らない。
今まで、何のために頑張って来たのだろう…。
ちょうど、氷見に道の駅ができるという話が持ち上がっていました。
そうだ、自分で店を持って販売しよう。
他には無い“ゑびす屋”名物を!
さっそく申し込んだのですが、よく考えると、
店を出すといっても何を売ればいいんだ?
アジやサバの干物では珍しくもなく、安く売ることは目に見えている。
鮮魚はもうこりごりだ。
新しくて店の目玉となる商品を開発すればいいんだ!
その想いで誕生したのが、最初の商品「醸熟ぶりステーキ」です。

オリジナル麹で醸した「醸熟ぶりステーキ」
今でも店の一番人気です。
笠井 健司
【商品開発物語】 ぶりステーキはこうして生まれた!
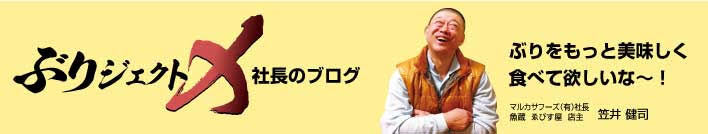

【商品開発物語】 ぶり焼きほぐし物語
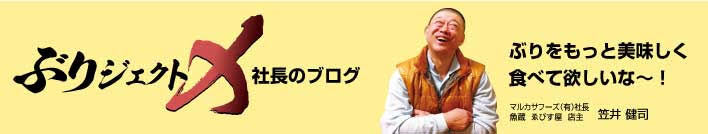

【商品開発物語】 縁起物として生まれた「ぶり茶漬け」